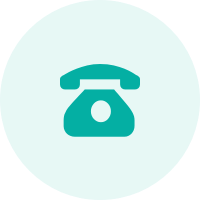预约国外,最快 1 个工作日回馈预约结果
医師にとってどこまでが“がん診療”か? 在宅医療と病院の相互連携が重要
記事1『がん患者さんのために在宅医療はどうあるべきか?在宅医療の進歩と課題について』では、在宅医療の進歩とメリット、課題点、そして病院の先生から見た懸念事項について、神奈川県立がんセンター 泌尿器科部長の岸田健先生と、小磯診療所理事長の磯崎哲男先生に対談していただきました。記事2では病院に勤務する医師側の課題を含め、在宅医療をさらに広めるにあたってどのような工夫が必要であるかについて、引き続き、岸田先生と磯崎先生にお話しいただきます。
病棟勤務医の課題――治療が終われば“我関せず”でよいのか?
岸田先生:急性期病棟に勤務する医師は、在宅や緩和ケア病棟に移ってからは患者さんに関与する必要がないと考える方向に向かっています。手術や抗がん剤治療が私たち専門病院の役割であり、がんに対する治療が終了して在宅医療や緩和ケアに移行したら、私たちの役割は終わりということです。これは決して患者さんを見捨てるわけではなく、在宅医療や緩和ケア病棟の先生に適切に引き継がれる体制が整ったからできることで、私自身もそういう方向にシフトしつつあります。
しかし、完全にスパッと切り替えてしまうことに疑問も残ります。こうした“治療が終了したら主治医はもう関知しない”という考え方が周囲に“標準的な捉え方”として受け止められ、緩和ケア病棟の先生や在宅医療の先生とうまく意思疎通が取れないケースもあります。
私が体験した残念な出来事を一例としてお話ししましょう。
私は若い世代に多い精巣腫瘍の患者さんを日々診療しています。ある患者さんはいったん完治しましたが、7年経ってから脳に転移してしまい、がんの治療は断念して終末期医療に移行しました。
私はその患者さんの主治医を長年務めていたため、最期まで診ていたい気持ちがありましたが、がんセンターに長期入院することは困難です。そのときにはご自宅で最期を迎える手段も緩和ケア病棟へ移る手段も構築されていたため、その方はいったん緩和ケア病棟に入院しましたが、適切な緩和治療で状態が落ち着いてきたためご自宅に帰れることになりました。帰宅後、私も様子を見に行きましたが、在宅診療の先生のおかげで元気そうに暮らされていました。
しかしある日、私が手術中のこと、がんセンターの別病棟からの電話で、その患者さんが亡くなったと告げられました。つまり、家で療養していると思っていた患者さんが、私が勤務しているがんセンターの病院内で最期を迎えたのです。
慌てて病棟に向かったところ、その患者さんは2日前に容体が悪化し、がんセンターの緩和ケア病棟に入院したとのことでした。ご家族が「岸田先生に会わせてください」と言っても「もう泌尿器科の診療は終わったから」と私には連絡しなかったそうなのです。患者さんが一度私の手元を離れたので、泌尿器科に連絡する必要はないと判断されたようです。緩和に移った患者さんは元の主治医とは無関係、それががんセンターでは普通の考え方になってしまっています。
このように、積極的治療が終了した患者さんとは縁が切れてしまう体制はとても寂しく感じました。しかしがんセンターの多くの医師は、これが特別おかしなことではないと割り切った考えを持っています。私も全ての患者さんを最期まで気にかけていられるわけではないので偉そうなことは言えないのですが、疑問が残りました。
磯崎先生:急性期病棟の先生には、おそらくシステマティックにならなければならない事情があるのでしょう。緩和ケア病棟の先生にも悪意はなかったはずです。ただ、岸田先生のように熱い心を持っている医師がいるほうが、私としては安心します。
医師は最初から最期まで患者さんの経過を見届けて初めてがん診療を学んだといえる
岸田先生:今後、医療はさらに役割分担を進めていくことになるのだろうと感じます。
急性期医療・慢性期医療の分業システムが構築され、私自身もそれに慣れてきて、最期を看取る機会は随分と減りました。ただ、本当にそれでいいのだろうかという思いがあります。
たとえば若手医師が病院で急性期の治療だけ学んでも、その患者さんがどのような最期を迎えるか、どのようにして最期に至るかを実際に診ていなければ実態が分かりません。知らないままで本当にがん診療を学んだといえるのでしょうか。
磯崎先生の場合は、病棟勤務時代に最初から最期までの経過を診たうえで緩和医療を選択されたので安心ですが、これからは最期まで見届けず患者さんの経過を知らない医師ばかりが育つのではないかという漠然とした不安があります。
なぜ横須賀で在宅での看取りが増えたのか――本来の役割に戻った医療体制
磯崎先生:岸田先生のご意見は、やはりベテランならではの視点に基づいていると感じます。
たとえば横須賀で在宅での看取りが増えた1つの要因には、この地域には急性期病棟が多く、慢性期病棟が少ないという点が関係します。つまり、急性期病棟ではあくまで急性期医療の役割を果たし、治癒を目指す治療が必要とされる方が入院するということです。急性期病棟では終末期の方をみることができないので、必然的に在宅医療の需要が高まり、在宅での看取りが増加しました。
岸田先生:割り切っていますね。
磯崎先生:ここに関しては一長一短がありますが、時代の流れからすればそうせざるを得ないでしょう。
岸田先生:医療費の抑制とベッドの回転率を上げなければならない日本の事情を、どうバックアップするかが課題になってきますね。
急性期医療と在宅医療がうまく連携するためには? 医師同士の交流を深めることが大切
磯崎先生:在宅医療と病院との連携を深めるためには、病院と在宅の双方が互いの現場を知り、より深い交流を重ねていくべきだと考えます。
病院の先生方が在宅医療の現場に来て在宅医療を経験していただければ、それ自体が、患者さんが退院された後の在宅医療計画のイメージとして役立ちます。
岸田先生:磯崎先生が病院へ出向いてくれるのと同じように、病院の医師は在宅の現場にどんどん出て、在宅医療とはどのようなものなのかを学ぶということですね。
アルバイト形式で在宅医療と病棟の相互交流を行い、理解を深める工夫
磯崎先生:たとえば、アルバイトとして訪問診療や外来診療を病院の先生方に行っていただき、退院後の患者さん方の療養状態を診ていただいてもよいでしょう。一方、私たち在宅医療側の人間も病院に出向き、在宅医療から再び入院となった患者さんへの対応を行えば、病院と在宅医療の双方に信頼関係が生まれ、効率のよい診療体制を構築することができます。
いずれは病棟主治医が引き続き訪問診療の一部を担っていくような形を確立していければと考えていますが、まだまだ道半ばといったところです。
岸田先生:記事1『がん患者さんのために在宅医療はどうあるべきか? 在宅医療の進歩と課題について』でお話しした三浦前部長は無償で在宅の現場に行っていましたが、その当時は時間に余裕があったから可能だったという面もあるでしょう。
磯崎先生がおっしゃるとおり、外勤という形で病院の医師が在宅の現場に出て一緒に診療できる体制が理想ですね。そうすれば患者さんご自身は自宅で過ごしながら、主治医と在宅医療の先生、両方の医師に診てもらうことができます。
病棟・在宅両方の医師が継続的に患者さんに会うことが大事
岸田先生:私は、患者さんが退院した後も患者さんとつながっていたいと考えています。三浦前部長を見習って、年に2~3人のペースですが、在宅医療に移行した患者さんの顔を見に伺っています。ただし、そのとき私はあくまでお見舞いに行っているだけであり、そこでの患者さんの治療は在宅医療の先生がするものだという意識が前提です。それでも患者さんは喜んでくださいます。
磯崎先生:実際に見ていて分かるのですが、病院の先生が患者さんのご自宅を訪問すると、患者さんは本当に喜ばれます。また逆のパターン、つまり患者さんが入院したときに私たち在宅医療の医師が病棟にお見舞いに行くと、患者さんは同様に喜んでくれます。
若手医師・医学生には在宅医療や終末期医療についてどのように指導すべき?
磯崎先生:役割分担が進むからこそ、今後は研修医や若手医師にも在宅医療に関する指導が必要となります。
私は小磯診療所にて医学生の受け入れと、大学で在宅医療の授業を行い、若手医師の教育に携わっています。たとえば小磯診療所の分院である並木小磯診療所では、横浜市立大学消化器科の先生にアルバイトとして勤務していただき、消化器系の患者さんへの訪問診療をしてもらっています。その先生は非常勤ですから急変には対応できませんが、その分は私たち常勤医がカバーすることができます。
病棟医と在宅医が一緒になり、相互に行き来できる体制を構築する必要がある
岸田先生:私も月に半日程度は在宅医療にあたる時間を設け、在宅に移行した患者さんを診たいと思っているものの、その余裕がありません。病院医師の在宅診療が診療報酬上も認められれば、病院としてもこの体制を認めやすくなり、病院の医師が在宅医療に関わる形が実現化するかもしれませんね。
磯崎先生のように、しっかりと在宅医療や若手医師の教育を担ってくれる医師がさらに増えれば理想的です。
磯崎先生:もちろん病棟の先生に在宅に来ていただくだけではなく、在宅医と病棟の先生の双方がお互いの施設に行き来できる体制をつくる必要があります。診療所の先生が病院で働き、病院の先生が診療所で働く。こうしたフレキシブルな体制の下でお互いの医療の実態を知り、学ぶことで、終末期医療の質は格段に上がると考えます。
岸田先生:今後はさらに病院と在宅医療の垣根をなくして、互いに交流していきたいですね。
在宅医療に迷いがある方に向けて――岸田健先生、磯崎哲男先生のメッセージ
磯崎先生:今ではご自宅で最期を迎えることができる時代になりました。患者さんのご家族は在宅医療に慣れるまで時間がかかりますが、患者さんを看取った後には満足感があるとおっしゃる方が多いです。私たち在宅医が自宅療養をお手伝いすることで、ご本人・ご家族の不安が減少するため、ご家族の方に在宅医療に協力していただけると考えます。
岸田先生:人にはさまざまな最期の迎え方があります。その中に在宅という選択肢があることを、より多くの方に認識していただきたいです。これからは在宅医療というイメージが、さらに浸透することを望みます。
また、最期を迎える場所について、病気になってから、あるいは終末期になってから考えるのではなく、普段から考えておいたほうがよいでしょう。いざというとき、人はどうしても混乱します。ですから、元気なうちに最期のことを考えられるように、病院側も情報提供を続けていきます。
磯崎先生:私は今回の対談で、岸田先生から医師としての矜持を学びました。
岸田先生:私はこれまで在宅医療の先生とここまで踏み込んだ話をしたことがなかったので、在宅医療の先生を見直すきっかけになりました。がんセンターから在宅医療に患者さんを移すとき、磯崎先生のような方ならば安心してお任せできますし、私が現在お願いしている先生方とも今後はより積極的に交流を深めていきたいと感じました。