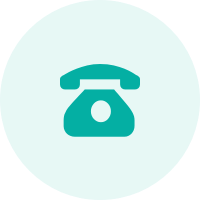预约国外,最快 1 个工作日回馈预约结果
がん患者さんのために在宅医療はどうあるべきか?在宅医療の進歩と課題について
がんと闘ってきた患者さんが最期を迎える場所としてご自宅を選ぶケースが増えてきています。これに伴い、自宅で医師の診療を受け、管理をしてもらう“在宅医療”の分野も著しく進歩・発展を遂げており、今では患者さんが自宅でご家族に見守られながら最期を迎えることも可能となりました。とはいえ、病院から在宅医療へ療養の場所を移す際に、それまで患者さんを担当してきた主治医の思いと在宅医療の先生の思いが同じ方向を向いていなければ引き継ぎがスムーズに進みません。今回は神奈川県立がんセンター泌尿器科部長の岸田健先生と、小磯診療所理事長の磯崎哲男先生に対談していただき、病院側・在宅医療側の2つの視点から、これからの在宅医療のあり方について考えていきます。
病院側から見た在宅医療の在り方
岸田先生:私はがんセンターに勤めて2016年で8年目になります。前任の大学病院の時代は、病院で最期を迎える方が圧倒的に多く、在宅医療はあまり発展していませんでした。特にがん患者さんの場合、ご本人が在宅療養を希望し、私たちがご自宅に帰してあげたいと思っても地域でがん患者さんを診る医師が少なかったため、自宅で最期を迎えることが困難でした。当時は療養型の病院で最期を過ごす方が多かったことを覚えています。
そのような時代、私の前任である三浦部長は、当時から在宅医療と緩和医療に積極的に関わっていました。帰宅を希望する患者さんを家に帰し、自宅で最期を迎えていただくために、休日やがんセンターでの仕事の後に自ら往診を行っていたのです。このことは今でも印象に残っています。
その頃から厚生労働省によって、“手術や集中治療が必要ではない方はできる限り療養型病院(緩和ケア病棟)へ回し、さらに在宅療養を増やす”という方針が推進されました。また、緩和ケア病棟の利用も増加したため、現在では急性期病院の一般病棟で看取る方の数が減少傾向にあります。
磯崎先生:緩和ケア病棟が増加し、緩和ケア病棟に行く方が増えているのですか。
岸田先生:はい。これには、緩和ケア病棟の回転率が上がったという点も関係しています。
以前は患者さんが一度緩和ケア病棟に入られると、半年や1年単位で病棟にいらっしゃることも多く、一度入院したら、最期までそこで暮らすという風潮でした。
今では緩和ケア病棟の方針が変わり、適切な緩和ケアにより状態が安定した患者さんは家に帰ることもできるようになりました。その背景には、在宅医療を担う医師が増え、患者さんやご家族、緩和ケア担当の先生も安心して家に患者さんを戻せるようになったというところがあります。その後そのまま在宅で最期を迎える患者さんも多くいらっしゃいます。ですから、病院で看取られる患者さんは少しずつ減少しているという印象です。
磯崎先生:確かに、小磯診療所にも年間数例、がんセンターから紹介があります。
最期をどこで迎えるか? 病院側からは在宅医療について患者さんに話をする
岸田先生:病院でも、在宅医療について患者さんにご説明するようにしています。
私はできるだけ早い段階で患者さんに「お別れが近くなったとき、最期まで病院にいるか、ご自宅で最期を迎えるかの二通りの選択肢があります。在宅医療を選んだ場合、自宅に往診の先生やヘルパーさんが来てくれますし、きちんと治療が受けられる体制が整っているので、ご自宅に戻られる方も増えています」とご説明し、在宅医療という選択肢があることを情報提供しています。
介護される方がいなかったり在宅医療では不安だと感じる方の場合、がんセンターの一般病棟では長期入院が難しいので、緩和ケア病棟に申し込むか、あるいはがんセンターに短期入院してから療養型病院を紹介する形になります。
患者さんのご希望が反映されるかどうかは状況によって異なり、在宅での最期を希望していたものの、入院中に容体が急変し、そのまま亡くなる方もいらっしゃいます。とはいえ、最期を迎える場所に、在宅という選択肢があることを早い段階で伝えておくと、患者さんには考える時間とチャンスが生まれます。
“看取る”場所の変化――在宅医療はどのように発展したのか
磯崎先生:現在の在宅医療は、訪問看護師による説明の方法や手順などの診療システムが徐々に確立されてきています。困っている症状に対応するまでの時間はかかりますが、現在は在宅医療用のデバイスが進化しており、在宅医療で実際にできることに、病院との差はなくなってきています。その意味では、在宅医療も進歩してきていると感じています。
また私の場合、患者さんが病院から在宅に移行する際に病院を訪れ、病院で主治医と一緒になって患者さんにご説明するスタイルを取っているため、患者さんがより安心して在宅医療に移ることができます。
※磯崎先生が考えられる在宅医療のあり方については磯崎先生のインタビュー記事もご覧ください。
岸田先生:在宅医療を始めるにあたって、患者さんが安心して在宅で診てもらえる仕組みの構築が重要ですね。
在宅医療で患者さんは幸せになれるのか? 在宅医療のメリット・デメリット
岸田先生:病院で患者さんを最期まで看取ることは、がんセンター本来の役割である手術や抗がん剤治療がますます増えているなかでは難しくなっており、在宅医療への移行は必要だと考えます。ただし、私は“患者さんが本当にそれで幸せか”ということも懸念しています。
“患者さんはずっと同じ先生に診てもらいたいという思いがあるのではないか”“状態が悪くなってから、人間関係が満足に構築されないまま在宅医療の先生に看取ってもらうことは最良なのか”この点が自分自身にとってはジレンマとなっており、特に何年も担当してきた患者さんが亡くなるときは、自分が看取ってあげたいという気持ちが強くあります。また、若い医師が急性期の治療のみを行い、患者さんの最期に寄り添う診療を経験しないことにも漠然とした危惧があるのです。
磯崎先生:岸田先生の考え方は、主治医制という面から見た医師の矜持ですね。
主治医である岸田先生が、病棟で最期まで見届けたいという気持ちはよく分かります。一方で、病気になる前の健康な方に対するアンケート調査では、全体の60%が自宅での療養を望んでいるという結果が出ています。また自宅での看取りは、専門家ではないご家族にとって大変ですが、多くの方は最期まで自宅で看てあげられたという満足感を得られるようです。自宅で最期を迎えることはご家族にとってもよい点があると考えます。
岸田先生:確かに、自宅で最期を迎えたいと希望する患者さんは多いのですが、患者さんが亡くなった後のフィードバックがないので、最終的にこれでよかったのだろうかと感じることがあります。
在宅医療の先生が丁寧な経過報告をくださったり、ご家族が私の元へ挨拶に来られ「在宅でよかった、困ったときはすぐに診てくれた」と言ってくださる場合もありますが、在宅医療や療養型病院に移られた患者さんはどのようなお気持ちだったのだろうか、としばしば考えます。
病棟勤務医から見た在宅医療への懸念――在宅医療を経済的側面から無理やりすすめていないか?
岸田先生:在宅医療の推進は“自宅で最期を迎えたい”という患者さんの希望を実現させるために必要ですが、一方で医療費の抑制という観点もあるでしょう。日本の医療を適切に継続させていくために役割分担は避けては通れないことであり、その方向性は正しいと考えます。しかし、三浦前部長の時代には“自宅で最期を迎えたい”という患者さんの希望に沿うために無償で行ってきたことが、現在はやや無理やり在宅医療に移行させる形になり、そこには患者さんの心のケアが抜けてしまってはいないかという漠然とした不安を感じることがあります。
私の患者さんをお願いしている在宅医療の先生方は、三浦前部長の時代から熱心に在宅医療に取り組んでいる先生が多く、私も安心してお任せしているのですが、再入院したときに「往診の先生は来てすぐ帰ってしまう」という話を患者さんやご家族から聞いたことがあります。在宅医療がどのような形で行われているのか、実際の現場をよく知らないのでそこに不安があるのも事実です。“在宅医療は儲かる”という話を聞いたこともあり、ビジネスライクに行っている先生もいらっしゃるのだろうかと思うこともあります。
磯崎先生:そうした在宅医療の医師がいる事実は残念なことですが、私の場合も、患者さんの容体に変化がなければ3~5分の診療で帰ってしまうことは珍しくありません。これは決してビジネスとして在宅医療を捉えているわけではないのですが、このことに対して実際にご家族から御批判をいただいたこともあります。
なぜすぐに帰ってしまうかというと、私たちは在宅医療での診療時間に緩急をつけているからです。
患者さんの容体が安定しているときは外来診療と同じで早めに診療を終えています。しかし、短い訪問時間でも日頃の状態が分かるので、具合が悪いときの容体の変化に気付きやすいのです。状態悪化の連絡があったときには早めに訪問し、診療、検査することにより患者さんの病状を把握し、内服薬治療、点滴注射剤治療、入院治療の3段階のいずれかが必要かを判断します。患者さんの具合が悪いときにこそ大量の医療資源を投入することで、治療方針を早期に決定することができるのです。
一度経験すると多くの方は納得してくださるのですが、病院での外来診療でも、緊急性が高くなければ数分で診療は終わります。在宅医療の体制はそれと似ています。
在宅医療の在り方は施設によってさまざま
磯崎先生:実は、在宅医療の施設自体はそこまで増えていません。看取りまで行おうとすると24時間365日稼働になるため、在宅医療を進められない医師もいるのではないでしょうか。
とはいえ、救急医療が必要な場合は通常の夜間救急体制で対応してもらうなど全てを自分たちの手で担わない形の在宅医療施設も多数存在します。もちろん、そうした形でも十分地域貢献になります。看取るだけが在宅医療ではありません。こちら側から通院困難な患者さんの元へアクセスするだけでも立派な在宅医療です。
在宅医療の患者さんは万が一のときすぐ病院に戻れるようにするべき?
岸田先生:入院と同じレベルで患者さんを診療できるならば、在宅医療はとてもよい仕組みだと考えます。ただ、患者さんやご家族、あるいは在宅医療の先生も何かあったときに不安でしょうから、在宅医療へ移行した後、患者さんに万が一のことがあってもすぐに入院できるように、後方支援ベッドを確保しています。がんセンターでは患者さんに専用のカードを手渡して、そのカードを持っている方であればいつでも入院できるという形を取っていますが、実際にこの制度を使う方は少なく、カード自体がお守りのようなものになっているのかもしれません。
磯崎先生: おっしゃるとおり、病院の先生方は患者さんをご自宅へ帰すときについつい「また悪くなったらいつでも相談してください」とアドバイスしてしまうようです。私もかつてはそうでしたが、ここにも1つ改善すべき点があります。
ときどき、私たちが患者さんのご自宅を訪問したときに患者さんがいらっしゃらないことがあります。ご家族に確認すると、具合が悪くなったので(在宅医に相談なしで)救急車を呼んで患者さんを入院させたといわれることがしばしばあります。
ですから私たちは、何かあればまず在宅医に相談していただきたいと病院にも患者さんにもお願いしています。入院が必要な際は、私たちから病院の先生に直接電話することで、スムーズに診療の段取りを整えることができます。
岸田先生:以前、別の在宅医療の先生と話したとき、「本当に危険なときは私たちが病院に連れていくので、『何かあったら戻ってきていいですよ』と言わないでください」と依頼されたことがあります。確かに、在宅医療の場で医師と患者さんが信頼関係を築くためには、そのほうがいいのかもしれませんね。
ただ、このことを言わなければ、患者さんは病棟の医師に見捨てられたと感じてしまう恐れもあります。この点が非常に難しいと考えています。
磯崎先生のように、患者さんが入院しているときからコミュニケーションを取ろうとするスタイルの在宅医療の先生が増えれば、今後は私たち病院の医師も安心して患者さんをお任せすることができます。
(記事2に続く)