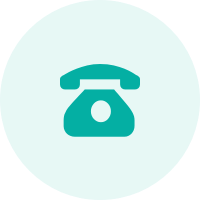预约国外,最快 1 个工作日回馈预约结果
肝硬変を含む肝臓病を見つける検査について
肝硬変の原因には、C型肝炎ウイルス、B型肝炎ウイルス、アルコールなどさまざまなものがあります。肝硬変にまで進行すると、幾つかの検査に特徴が現れてきますが、明確な数値などの定義はありません。では、どのような検査が行われるのでしょうか。湘南藤沢徳洲会病院の岩渕省吾先生に、肝臓病の検査について引き続きお話を伺いました。
肝臓病の検査
肝臓病にかかわる検査としては、血液検査と画像診断、さらに組織検査が行われます。以下に詳しく説明します。
血液生化学検査
肝臓に関する血液検査には、赤血球・白血球・血小板などの血球系の検査、血液の凝固系の検査、肝機能を含む生化学検査、ウイルスや免疫状態などを知る血清反応などがあります。
肝臓の異常を知ることができるのはまず血液生化学検査であり、なかでもGOT(AST)、GPT(ALT)、γGTPを調べることはとくに有名で、健康診断の採血項目にも必ず入っています。これらは肝細胞内にある酵素で、肝炎を起こしたり、脂肪肝など肝細胞に異常が現れると、細胞から血中に逸脱するため高くなるのです。
特にGPTは肝細胞に特異性が高く(肝臓がダメージを受けたときに上がりやすい)、GOTは心筋や筋肉にも含まれるため、心筋梗塞や強い筋肉疲労などでも上昇します。ただし、肝硬変まで進行すると肝炎自体は沈静化するため、両者ともあまり上がらなくなります。つまりGOT、GPTは、正確には「肝臓の機能」を表すというよりも「肝炎の程度や肝細胞自体の異常」を表しているのです。
肝機能という点では、肝臓で作られ身体で最も重要なタンパクである「アルブミン」が重要です。肝硬変の進行程度を表す分類について後述しますが、ここでも血清アルブミン値が「3.5(g/dl)以上」「2.8以下」「その中間」の3つの場合に大きく分けられています。
もうひとつ肝硬変の程度を測るうえで重要なことは、黄疸のもとである「ビリルビン値」と肝臓で作られる「血液凝固因子」です。赤血球中のヘモグロビンから作られるビリルビンは肝機能の最も重要な部分であり、肝硬変においても血清ビリルビンが増加するのは悪い徴候です。ちなみに、皮膚や目が黄色いなどの黄疸の徴候が現れるのは、血清ビリルビンが3(mg/dl)以上のときで、5以上になると誰でも明らかに黄色いとわかる状態になります。ただしビリルビン増加にも色々なパターンがあります。必ずしも肝臓病の末期だから上がるというわけでは実はありません。血液の病気などでも上がることがあります。
また、肝臓で作られる血液凝固因子のプロトロンビン(PT)活性も、肝機能の評価としてよく用いられます。PT低下の程度は肝硬変の評価にも組み込まれており、肝硬変が悪くなると出血しやすくなることの一因になります。
肝硬変かどうかを知るために最も簡単で意味ある基準は、血小板数でしょう。肝硬変になると血小板が減ります。それは、肝硬変では肝臓の反対側にある脾臓が腫れ、その機能が増す(脾機能亢進)からです。本来脾臓は免疫細胞の集まりですが、老廃した血小板などの血液細胞の処理も行っています。肝硬変になって肝臓が硬くなると、脾臓からの血液が肝臓に入りにくくなり、脾臓に圧力がかかって腫大してきます。腫大した脾臓が血小板や白血球を過剰に壊し、血小板や白血球減少を招くのです。
C型慢性肝炎でもアルコ-ル性肝障害でも、血小板数が12万(/mm3)を下回ると肝硬変への進行が疑われ、画像診断に注目します。10万を割るとまず肝硬変になっているといえます。肝硬変では血小板が5万以下に減る方もいます。ただしこの場合の血小板の低下は肝機能とは関係なく、肝硬変症の合併症として重要な、門脈圧亢進症や食道静脈瘤(後述)と関係しています。したがって脾臓の塞栓療法(PSE)や脾臓摘出を行うと、血小板や白血球は正常な数値ないしそれ以上にも増えます。
画像診断
肝・胆・膵に関する画像診断では、主に以下の4つの検査が行われます。
- 超音波検査
- 腹部CT検査
- 腹部MRI検査
- 内視鏡検査
超音波検査は最も簡便な検査で、最初に行われます。肝臓や脾臓の形や大きさ、表面の形状などがわかります。最近では超音波を用いて、肝臓に入る太い血管(門脈)の血流状態や、肝臓の硬さも測られるようになりました。
X線CT(腹部CT検査)もよく行われます。この場合は、造影剤を注射して肝内の血流を染めて撮影します。肝臓のみならず、肝硬変で発達するお腹の異常血行や静脈瘤も検出できるため、肝硬変・肝癌の評価に重要です。
MRI(腹部MRI検査)も肝臓癌の診断で一躍、有名になりました。この方法ではプリモビストという新しい造影剤を注射し、肝臓での排泄過程をみて早期の肝癌の診断や、「MRCP」という方法で胆管や膵管の撮影も行うことができます。この10数年、コンピュータや物理光学の進歩の恩恵により、医学系画像診断の発展には目覚ましいものがあります。
また、内視鏡検査も肝硬変の合併症のチェックには必要な検査です。肝硬変症も進行すると、食道や胃さらに直腸や肛門周囲の静脈が発達し、これが破れると大出血を起こすことがあります。したがって、事前に内視鏡で観察しておく必要があります。
肝硬変の場合、画像診断を行うと以下のような特徴的な所見が見られます。
- 肝臓の表面が凹凸不整になる。
- 肝臓の辺縁が丸くなり、右葉が小さく萎縮し、左葉が小さくなった右の肝臓の機能を補完すべく代償性に腫大する。(肝臓は右横隔膜の下にある大きな右葉と、みぞおちにかかる小さな左葉に分かれる)
- 肝臓内部は不整、ざらざらになる。
- 脾臓が腫れ、肝臓につながる血管が太く蛇行する。
- 腹部異常血行路:お腹中の血流は、通常はいったん門脈という太い血管に集まり肝臓に流れるが、肝臓が硬くなると門脈血は肝臓に入りにくくなり、その流域の静脈が拡張して、正常にはない見られない静脈が発達する。
- この静脈の腫れが、内視鏡で食道ないし胃静脈瘤として観察される。最近では内視鏡治療技術がすすみ、あらかじめ胃カメラで静脈瘤の有無を観察しておき、静脈瘤の太さが増したり、発赤が出てきた場合には、内視鏡的に血管の硬化療法を行う。
肝硬変の重症度を表す指標
検査を行ったあと、肝硬変の程度を表すためには以下のような「Child-Pugh分類」という表が用いられます。略称で「Child分類」といわれます。
この表では、それぞれの状態や血液検査の結果がどこに当てはまるかを見ていき、当てはまった場所の点数(5カ所)を合計します。Grade A、B、Cの順番で状態が悪くなっていきます。
また、この分類は古くからある分類ですが、肝硬変の患者さんの肝臓の余力(予備能といいます)を示すものとして、世界共通の指標として今も用いられています。
肝硬変の定義について
肝硬変には上に述べたような検査がありますが、冒頭で説明したように、検査所見からわかる肝硬変の定義には、明確なものはありません。なぜなら肝硬変の検査は、生化学的(血液検査から考える)・画像的(CTやエコーから考える)・組織的(肝臓に針を刺して生検をし、組織を顕微鏡で見て考える)など、複数の観点をふまえて総合的に判断されるからです。
最も正確なのは肝生検などの組織検査(体の組織を採取して行う検査)であり、「偽小葉」(正常の肝小葉とは違う構造)や再生結節が作られていれば、間違いなく肝硬変と診断できます。かつては「腹腔鏡検査」で肝臓の表面を直接見て再生結節の状態から診断していた時代もありました。
しかし慢性肝炎から肝硬変に至る過程はとても長く、その境界領域(慢性肝炎とも肝硬変ともいえる状態)もあります。そのため現在では、肝硬変と確定診断をすることよりも、臨床的な特徴をきちんと捉えて「原因はウイルスなのか、アルコールなのか」という観点でしっかりと原因を探し出し、治療をしていくことを重要視する流れに変わっています。
また、かつてはC型肝炎のインターフェロン治療(生体がウイルスに感染したとき、細胞が反応して作られるタンパク質を薬として、体内に大量投入する治療法)を行う場合に、「肝生検」で肝臓の組織検査を行わないと保険が適用にならない時代がありました。その後医療制度が改善され、肝生検を行わなくてもインターフェロン治療が保険適用となりました。その影響でC型肝炎の場合、肝生検は全般的に実施されなくなってきました。
しかし、今後は肝硬変が「治る病気」になりつつあります(参照:「肝硬変の治療―原因への治療と合併症への治療」)。そのため、肝臓からウイルスが消えたあとでも、肝硬変で繊維化した肝臓がどのように改善していくのか肝生検を実施してきちんと見極めていく必要があります。また、肝硬変の繊維の質次第で肝臓がんになりやすいか、なりにくいかを予測できる可能性もあり、肝生検の必要性が復活するともいわれています。
肝硬変の検査では、血液検査と画像検査が主に用いられます。
血液検査
血液検査で主に調べるのは以下です。
- 赤血球・白血球・血小板などが減少しているか
→脾臓の機能が亢進(強くなりすぎる)ことで、これらの3つが壊されてしまいます
- 総ビリルビンの上昇が見られるか
→肝臓に胆汁がうっ滞(胆汁の流れが疎外されている状態)してしまうことによります
- プロトロンビン時間(PT)の延長・Alb(アルブミン)低下・ChE(コリンエステラーゼ)低下が見られるか
→肝臓の機能が低下し、タンパク質の産生が落ちることによります
画像検査
画像検査では、主に以下の2つの検査が行われます。
- 超音波検査
- 腹部CT検査
これらの検査をすると、主に以下の4つの所見が見られます。
- 肝臓の表面が凹凸である
- 肝臓の辺縁が丸くなっている
- 腹水
- 脾臓の腫れ
肝硬変の程度を見るために
検査をした後には、以下のような「Child-Pugh分類」という表が肝硬変の程度を調べるために用いられます。略称で「Child分類」と言われます。
表の見方は、それぞれの状態や血液検査の結果がどこに当てはまるかを見ていき、当てはまった場所の点数(5カ所)を合計します。Grade A、B、Cの順番で状態が悪くなっていきます。
1点2点3点
肝性脳症なしⅠ度~Ⅱ度Ⅲ度~Ⅳ度
腹水なし軽度中等度
血清ビリルビン(mg/dL)<2.02.0~3.0>3.0
血清アルブミン(g/dL)>3.52.8~3.5<2.8
プロトロンビン時間(%)>8050~80<50
Grade A: 5~6点、 Grade B: 7~9点、 Grade C: 10~15点
また、この分類は別記事「肝硬変の予後と余命について」で説明するように予後(治療後の容体)予測に用いられていたこともありますが、現在ではあまり使われていません。
肝硬変の定義について
肝硬変にはこれらの検査がありますが、冒頭で説明したように、検査所見からわかる肝硬変の定義には、はっきりしたものがありません。なぜなら肝硬変の検査は、生化学的(血液検査から考える)・画像的(CTやエコーから考える)・組織的(肝臓に針を刺して生検をし、組織を顕微鏡で見て考える)な観点など、異なる見方をされてきたからです。
病理学者からすると「偽小葉」(正常の肝小葉とは違う小葉)がなければ肝硬変とは言わないと考えられていましたし、かつては「腹腔鏡検査」という検査で肝臓の表面の状態を直接見て診断していた時代もありました。
しかし現在では、肝硬変はきちんと確定診断をすることが重要ではなく、臨床的な特徴をきちんと捉えて、原因はウイルスなのか? アルコールなのか? という観点でしっかりと原因を探し出し、治療をしていくことが大切という流れに変わっています。
また、かつてはC型肝炎のインターフェロン治療(生体がウイルスに感染したとき、細胞が反応して作られるタンパク質を薬として、体内に大量投入する治療法)をする場合に、肝生検で肝臓の組織を顕微鏡で見ていないと保険が適用にならない時代がありました。
しかし医療制度が改善され、その後、肝生検で組織を見なくても保険適用でインターフェロン治療が受けられるようになりました。それから、肝生検は全般的に実施されなくなってきました。
しかし、今後は肝硬変が治る病気になりつつあります(参照:「肝硬変の治療―原因への治療と合併症への治療」)。そのため、肝臓からウイルスが消えたあとでも、肝硬変で繊維化した肝臓がどのように改善していくのか肝生検を実施してきちんと見極めていく必要があります。また、肝硬変の繊維の質次第で肝がんになりやすいか、なりにくいかを予測できるとも言われています。