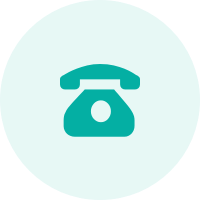预约国外,最快 1 个工作日回馈预约结果
ピロリ菌による胃潰瘍の治療-除菌療法とはどのようなものか
胃潰瘍には非ステロイド性抗炎症薬が原因となるNSAIDs潰瘍のほか、主に小児期に感染したピロリ菌が原因となるHp潰瘍があります。これら2つの胃潰瘍の治療方針は異なっており、Hp潰瘍の治療においてはピロリ菌の除去が必要になります。本記事では、ピロリ菌による胃潰瘍の治療の詳細について、国際医療福祉大学塩谷病院消化器内科部長の山根建樹先生にお伺いしました。
潰瘍の治療
血液検査や胃生検組織を用いた迅速ウレアーゼ試験などにより、胃潰瘍の原因がピロリ菌によるものか診断します
潰瘍に対する治療としては、主に胃酸の分泌を抑えるPPI(プロトンポンプ阻害薬)やP-CAB、H2ブロッカーなどを投薬します。ピロリ菌の除菌のためには複数の薬剤を内服せねばならないので、潰瘍による吐き気や心窩部不快感などの症状が落ち着いてから除菌薬を投与した方が効率的です。
ピロリ菌の除菌療法とは
潰瘍による症状がある程度治まったら、ピロリ菌の除菌を行います(除菌前には内視鏡検査~病理組織学的検査により、必ず胃がんを鑑別します。なぜなら、胃がんは除菌では治るものではないうえに、早期がんに対して安易に除菌療法を行ってしまうとがんの存在診断が難しくなることもあるからです)。
ピロリ菌の除菌には、胃酸の分泌を抑えるPPI(プロトンポンプ阻害薬)ないしP-CAB(新薬でPPIの1種)と2種類の抗菌薬を使用します。日本では、消化性潰瘍に対する除菌療法は2000年に保険認可されています。その後胃癌の発症予防のため慢性胃炎にも適応が拡大されました。現在では1回目の除菌不成功例に対する2次除菌まで認可されています。
※3次除菌以降は自己負担となります。
1次除菌
使用する薬剤:PPIないしP-CAB・アモキシシリン(抗生物質)・クラリスロマイシン(抗生物質)
服用期間:1週間
除菌率:70~90%
除菌薬投薬後、最低4週間たってから(これ以内では正しい結果が出ません)尿素呼気試験または便検査(Hp便中抗原測定)を行って除菌判定をします。なおPPIやP-CAB投与を続けると正しい判定ができないため、これらの薬は判定の最低2週間前から中止します(実際には除菌が不成功の場合もあるため、判定に差し障りのないH2ブロッカーに切り替えて潰瘍治療を続けます)。除菌不成功の場合は、2次除菌を行います。
2次除菌
使用する薬剤:PPIないしP-CAB・メトロニダゾール(抗原虫薬)・アモキシシリン(抗生物質)
服用期間:1週間
除菌率:90%台
除菌薬の主な副作用
前項で挙げた除菌薬の服用中には、次のような副作用が現れることがあります。
下痢:出血性腸炎をきたすこともあります。ただし、耐性乳酸菌整腸剤などを併用することで、ある程度防ぐことができます。
口内炎
皮膚の発疹
また、除菌療法が成功した後も1年ほどは胃酸分泌が安定せず、胸やけなどが現れることがあります。このような症状にはPPIなどを処方することで対処します。
画像でみるピロリ菌除菌療法による胃潰瘍の治療
左図は、再発を繰り返していた胃角部の線状潰瘍です。ピロリ菌除菌後は、抗潰瘍薬を投与することなく、右図のように瘢痕状態を維持できています。
ピロリ菌陽性のNSAIDs潰瘍
前項ではピロリ菌のみが原因となっている胃潰瘍について紹介しました。次にNSAIDs潰瘍ですが、ピロリ菌陽性者では陰性者に比べて潰瘍の発生率が高まります。下記にピロリ菌とNSAIDsの潰瘍発生の相対危険度を示します(Hp陰性でNSAIDsの服用がない場合を1としています)。
【HpとNSAIDsの消化性潰瘍発生の相対危険度】
- Hp(-)・NSAIDs(-): 1
- Hp(+)・NSAIDs(-): 18.1
- Hp(-)・NSAIDs(+): 19.4
- Hp(+)・NSAIDs(+): 61.1
この写真は、ピロリ菌陽性でバイアスピリンを服用していた方の胃角部にできた、大きく深い潰瘍の活動期を撮影したものです。2つのリスクが重なって生じた胃潰瘍は、このように深刻なものになることがあります。治療はHp除菌を含めて行いますが、潰瘍治癒後もバイアスピリンの継続服用が必要であるため、再発の予防にPPIの服用を続けてもらいます。
ピロリ菌除菌後の注意と再発のリスクについて
除菌成功後のピロリ菌再感染率は0.2%未満と極めて稀です。またNSAIDsを服用していないHp潰瘍であれば、再発する危険性はごくわずかです。しかし除菌後も、定期的な上部消化管内視鏡検査(GIF)による結果観察が望まれます。というのも、頻度は稀ですが、除菌後にも潰瘍が再発することもあり、また除菌は胃癌の発症を抑えますが、除菌前に肉眼で観察することが不可能であった小さながんが発育してきて見つかることもあるからです。