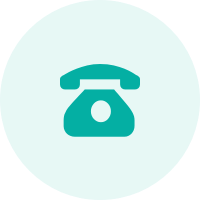预约国外,最快 1 个工作日回馈预约结果
心房中隔欠損症とは――主な症状や診断のための検査
何らかの先天性心疾患があって生まれてくる確率は約100人に1人と決して珍しくはありません。その中でも心房中隔欠損症は割合が多い病気の1つとして知られています。心房中隔欠損症の症状や発見されるきっかけ、実際に行われる検査などについて、札幌心臓血管クリニック 循環器内科部長/ストラクチャーセンター長の八戸 大輔先生にお話を伺いました。
心房中隔欠損症はなぜ・どのくらいの頻度で起こるのか
心臓は4つの部屋(右心房・右心室・左心房・左心室)から構成されています。そのうち右心房と左心房を隔てる壁に、生まれつき孔が開いてしまう病気のことを心房中隔欠損症といいます。心臓に生まれつき何らかの異常を伴うものを総称して先天性心疾患といい、おおむね100人に1人の割合で発症するといわれています。その中でも、心房中隔欠損症は先天性心疾患の約7%を占める主要なものの1つです。
心房中隔欠損症を含む先天性心疾患の多くは、心臓の発生過程になんらかの異常が生じることで起こります。遺伝性や家族性(血縁関係にある家族に同じ病気が認められること)は一般的には認められていません。特定の1つの遺伝子のみが原因となるのではなく、遺伝子異常や環境因子など複数のリスク因子が重なることで病気を発症すると考えられています。具体的な環境因子としては妊娠早期に風疹などの感染症に罹患することや薬物、喫煙などが昔から知られていますが、これまでの研究で心臓の発生・分化に関わる分子異常が関連していることについても明らかになっています。
症状・合併症の程度や出現時期には個人差がある
心房中隔欠損症では、欠損孔(心臓に開いた孔)を通って血液が過剰に右心系(右心房・右心室)や肺の血管に流れ込み、心臓や肺に負担がかかって以下のような症状が現れます。
【心房中隔欠損症でみられる主な自覚症状】
- (子どもの場合)体重の増え方が遅い
- (子どもの場合)ほかの子に比べて小柄な体格
- 運動時に息がきれやすい
- 風邪をひきやすい
など
ただし、心房中隔欠損症の患者さんの多くは、幼児期・小児期にはほとんど無症状です。たとえ症状があったとしてもこの病気に限られたものではないため、見逃されることが珍しくありません。また、症状が出る時期は欠損孔の大きさにも左右されます。欠損孔が小さければ、閉鎖せずとも血液が過剰に流れている状態に右心系が適応し、ほとんど症状が現れないまま生涯を終えることもあります。実際に子どものころは症状を訴えて病院を受診するというよりも、健康診断で心雑音を指摘され、病院の精査で診断がつく場合が多い傾向にあります。
しかし、治療をしないまま時間がたち成人期・中年期に差しかかってくると、徐々に心臓への負担が蓄積し、右心房・右心室の拡大、弁の変形、肺血管への影響が顕著となります。この結果、多くの患者さんが何らかの症状を自覚します。
これらによって起こるさまざまな合併症も問題となります。たとえば、心臓の壁の筋肉が引き延ばされることで、心臓の壁を通る伝達系が障害されれば心房細動や不整脈が生じます。さらに、過剰な血液により心臓の弁が変形してしまうことで起こる心臓弁膜症や、肺血管への血流が多い状態が続いた結果、血管が目詰まりして起こる肺高血圧症なども心房中隔欠損症に伴う合併症といえます。
診断・評価のための検査
(1)聴診
心房中隔欠損症の患者さんの多くが健康診断の聴診で心雑音を指摘されて病気が見つかります。心房中隔欠損症では肺動脈の狭窄があり、欠損孔を通って左心房から右心房に血液が流れることで、右心房から右心室への入り口である“三尖弁”を通過する血流が増加します。すると、流れる血液の量に対して三尖弁の大きさが相対的に小さくなってしまい、心雑音が聞こえるようになります。
(2)心電図
心電図とは体の表面に貼った電極から心臓の筋肉を流れる電気を記録する検査で、不整脈や心筋の循環不良(狭心症)、心筋の壊死(心筋梗塞)などの病気を発見するために行われます。心房中隔欠損症では右軸偏位*、右脚ブロック*、右室肥大といった所見を認めることがあります。健康診断での心電図の異常から診断がつくことも珍しくありません。
*右軸偏位:心臓を流れる電気の向きは通常右上から左下に向かい、この向きを電気軸と呼ぶ。これが右に偏った状態。
*右脚ブロック:心臓の刺激が伝わる系路の中で、右室の興奮伝導路(右脚)が障害されている状態。
(3)胸部X線写真
胸部X線写真では、右心房・右心室への血流が増えることによる心拡大が確認できます。肺動脈を流れる血液量も増加することで主肺動脈が拡大し、肺血管も目立ってみられるようになります。
(4)経胸壁心エコー図検査(TTE:Transthoracic echocardiography)
心房中隔欠損症の診断・治療方針決定のためにまず行われる検査が経胸壁心エコー図検査です。欠損孔の位置や大きさ、欠損孔を通る血流の程度、肺高血圧症の評価、弁狭窄・弁逆流、心機能などさまざまな情報を得ることができ、術後の心臓の状態評価や管理にも役立ちます。さらに、X線を用いたり体内に管を通したりする必要もないため、比較的患者さんへの負担も少ないことが特徴です。
(5)経食道心エコー図検査(TEE:Transesophageal echocardiography)
経食道心エコー図検査の基本的な仕組みは経胸壁心エコー図検査と同様ですが、その特徴は、食道という心臓から非常に近い場所から超音波を当てることで、より精細に心臓の情報を得られることです。最近では心房中隔欠損症に対する治療としてカテーテルを用いた方法が普及してきましたが、その適応を決定するうえで必須の検査となっています。
(6)CT検査
CT検査は高い空間分解能(近い距離にある2つの物体をそれぞれ独立した2つのものとして区別できる力)を持ち、エコー検査だけでは欠損孔がはっきり評価できないような場合、周囲構造物との関係をみながら冠動脈の形や心室機能を詳細に評価することに役立ちます。詳細な画像を得ることできます。また近年では機器の進歩により、短い時間での撮影ができるようになり、検査による被ばくを抑えることも可能となっています。
(7)心臓カテーテル検査
太ももの付け根などから血管にカテーテルを挿入し、心臓や大血管の形、血液の流れ方などを調べる検査です。超エコー検査やCT検査が発達してきたことにより、心臓カテーテル検査の担う役割は変化しつつあり、心房中隔欠損症そのものの治療適応を判断するうえでは必ずしも必須の検査ではなくなりました。ただし、肺高血圧症や冠動脈病変などの合併症が疑われる場合は、患者さんの容体に応じて心臓カテーテル検査を行うことが勧められます。
(8)血液検査
心房中隔欠損症の診断自体には直接関わりませんが、全身状態の把握のために血液検査も行われます。手術や心臓カテーテル検査・治療を行う場合には肝機能や腎機能、貧血などのリスク評価を事前に行います。
経過観察中も定期検査での心臓評価を欠かさずに
心房中隔欠損症は早期治療が必ずしも予後の改善につながるとは言い切れず、適切な治療のタイミングは患者さん一人ひとりの心臓の状態によって異なります。病気の発見から亡くなるまでまったく症状が現れないこともあれば、すぐに治療が必要になる方もいます。そのため心房中隔欠損症が見つかったら、まずその時点で治療の必要性を確認することが大切です。発見当初は経過観察が適応になっても徐々に病気が進行し、途中で治療が必要になる患者さんも中にはいらっしゃいます。たとえ症状がなく、現時点では治療を受ける必要がないと判断された患者さんでも、定期的な受診や検査を行い適切な治療タイミングを逃さないことが重要です 。