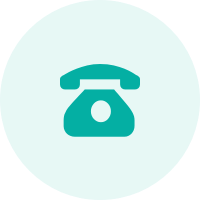预约国外,最快 1 个工作日回馈预约结果
胆道閉鎖症の治療と発展――腹腔鏡下手術で肝移植が不要になる時代を見据えて
胆道閉鎖症は、胆管が何らかの原因で閉塞、破壊、消失しているという難病であり、肝門部空腸吻合術(葛西手術)という劇的な術式が確立されていなかったころは、ほとんどの胆道閉鎖症の子どもが命を落としていました。肝門部空腸吻合術が行われることによって多くの子どもが元気に成長できるようになりましたが、この肝門部空腸吻合術のみで20歳まで生存できる患者さんは全体の約半数にとどまっているのが現状で、根治のためには胆道閉鎖症の患者さんは肝移植を受ける必要があります。
こうした状況のなか、名古屋大学医学部附属病院小児外科教授の内田広夫先生と、同院小児外科講師の田井中貴久先生は腹腔鏡下での肝門部空腸吻合術を行っています。本手術は臨床研究段階ですが、確定診断をつけるところから根治術まで低侵襲(体への負担が少ないこと)手術で完遂できるため、大きな意義があります。また積極的に腹腔鏡下での再手術も行っています。胆道閉鎖症の治療と発展について、内田広夫先生と田井中貴久先生にお話しいただきました。
この記事で書かれていること
- 肝門部空腸吻合術(葛西手術)が登場し、胆道閉鎖症は“治療できる病気”になった
- 胆道閉鎖症はなるべく早期に手術をすべき
- 生後90日以内に手術をすれば術後の黄疸消失率は著しく低下しないことが知られている
胆道閉鎖症の治療――肝門部空腸吻合術(葛西手術)について
胆道閉鎖症は、閉鎖している部位によって総胆管閉塞型(Ⅰ型)、肝管閉塞型(Ⅱ型)、肝門部閉塞型(Ⅲ型)に大きく分類されます。
これらのうち、肝臓の胆管(肝管)がしっかりと確認できる症例に対しては肝管空腸吻合術、肝管が確認できない症例に対しては肝門部空腸吻合術(この手術を開発した葛西先生にちなみ、葛西手術とも呼ばれています)を行います。
ほとんどの症例は肝外胆管の吻合が難しい吻合不能型であり、肝門部空腸吻合術が行われます。
肝門部空腸吻合術(葛西手術)とはどのような手術?
胆道閉鎖症では総胆管がないか、または非常に細くなっている
簡潔に述べると、肝門部空腸吻合術(葛西手術)とは肝門部(本来では動脈、門脈、胆管が1か所に集まり、肝臓に入っていく場所)に腸を張り付ける手術です。
胆道閉鎖症の患者さんには胆管(肝臓で作られる胆汁を流すための通り道)がないので、手術によって肝門部に腸を張り付け、そこから胆汁が流れるように治療します。
1960年代に肝門部空腸吻合術(葛西手術)が登場・実施されるまでは、ほとんど全ての胆道閉鎖症の患者さんが生まれてから1年と経たず肝硬変を発症し、亡くなっていました。肝門部空腸吻合術(葛西手術)が登場し(なおかつ肝移植が始まってから)、胆道閉鎖症は“治療できる病気”になったのです。
胆道閉鎖症の手術のタイミングはいつがベストか?
黄疸が進行し、胆汁性肝硬変に至ると、手術治療の成績が悪くなることが今までの全国統計から示されています。
インターネット上などでは、患者さんの生後60日以内に肝門部空腸吻合術(葛西手術)を施さなければ手術成功率(術後の減黄率)が低下するという情報を多く目にしますが、正確には生後90日以内に手術をすれば術後の黄疸消失率は著しく低下しないことが知られています。
胆道閉鎖症に対してなるべく早期に手術をするべきであることは間違いありませんが、手術日の数日の違いはそれほど大きな意味を持たないため、急ぐよりは万全の準備をしてから手術を行ったほうがよいと考えます。
腹腔鏡下肝門部空腸吻合術
名古屋大学病院の手術法とは?
現在、多くの施設では開腹で胆道閉鎖症に対する手術を行っていますが、当院では腹腔鏡下で胆道閉鎖症に対する手術を行います。
腹腔鏡下肝門部空腸吻合術の特徴
腹腔鏡下手術は高度な技術を必要とするものの、リスクの低い方法です。開腹手術と比較して少し手術時間が長くなりますが、侵襲性が低く、もちろん術創は小さく、出血量も少ないという特徴があります。
これに加えて、腹腔鏡下手術は“手術室に入ったスタッフ全員が手術の様子を見られる”というメリットがあります。
子どもは体が小さいので、小児外科手術では総じて術野が狭くなってしまいます。たとえば開腹での肝門部空腸吻合術の場合、術野をしっかりと見ることができるのは執刀医だけで、前立ちの医師(第一助手)はかろうじて術野を確認できる程度です。
一方、腹腔鏡下肝門部空腸吻合術ではカメラで撮影している術野をモニターに映しださなくては手術が行えず、さらに術野は拡大して画面に映しだされるため、スタッフ全員で手術の様子を共有することができます。どの部位をどのように剥離し、切離しているかをみんなで見ることができますから、執刀医が若手医師に技術を伝えるには最適な方法です。「今からどの部分を切っていくか」などを正確に説明しながら手術を進められるのです。また、後日手術について検証するにあたり、ほぼ全ての画像が録画されているので重要な証拠を残すことにもつながります。
このような意味で、腹腔鏡下手術は現代向きの手術法ということができます。
実際の腹腔鏡下手術の動画
胆道閉鎖症に対する腹腔鏡下手術はどこで受けられるのか?
腹腔鏡下肝門部空腸吻合術を5例以上行っている施設は、2016年時点で名古屋大学病院および順天堂大学病院の2施設のみ
2016年10月の時点で、名古屋大学小児外科では18例の胆道閉鎖症の患者さんに腹腔鏡下肝門部空腸吻合術を行ってきました。この手術を受けた方のうち、治療後の黄疸消失率は約72%、術後1年目での自己肝生存率*(黄疸なし)は約67%という結果が出ています。この治療成績は胆道閉鎖症研究会で明らかにされている開腹手術と同等です。腹腔鏡下胆道閉鎖症手術は開腹手術と成績が同等で、術創や出血などが少ないため、施行する意義が十分にあると考えています。
*自己肝生存率:後述する肝移植なしで、自分の肝臓を残したまま生活できる状態
また、胆道閉鎖症に対する腹腔鏡下手術は2018年度の診療報酬改定により保険適用されており、保険下で実施可能です。
小児は手術が多様で、年に1回という手術も珍しくないのですが、そのような手術の多くは、保険収載されていません。手術は少ないものの確実に存在し、いわゆる定型的な手術の1つとなっています。そのような手術の場合は、一番近い手術術式で保険請求を行ってきたので、小児外科はもともと保険収載に関しては、かなり寛容でなければ成り立たない科だったことがあります。
現状ではそのように保険適用となっていない術式はかなり減ってきており、内視鏡手術も今、順次保険収載されている最中だと考えます。
胆道閉鎖症の根治治療法“肝移植”
肝門部空腸吻合術のみで20歳まで生存できる患者さんは全体の約半数にとどまっているのが現状で、手術は肝移植を踏まえて行われる治療ということができます。
肝移植は、主に下記の症状が継続する場合に適応となることがあります。
- 黄疸が改善しない
- 胆管炎を繰り返す
- なかなか成長・発達しない
- 肝硬変による合併症が起きる
- 肺機能が低下する
胆道閉鎖症に対する肝移植治療の成績は非常に良好で、5年生存率が9割を超えます。最近では、移植後の新たな長期合併症が報告されるようになってきていますが、このことを加味しても、移植は胆道閉鎖症の最終的な根治術として十分に確立された治療だと考えています。
腹腔鏡下での再手術で自分の肝臓の長期温存が可能になる?
先に述べたように、胆道閉鎖症においてはいったん手術して、黄疸が改善しない場合に移植を検討する施設が多いのですが、当院では移植よりも腹腔鏡下での再手術を優先的に考えます。
過去に当院で行ってきた多くの開腹手術の症例の積み重ねから、再手術を行うことで術後減黄(黄疸が改善すること)が得られ、患者さん自身の肝臓で長期間生活ができることが分かってきたからです。現在までに、再手術を行った約25%の方が自己肝(自分の肝臓)で長期生存していることが分かっています。
そのため、当院では、腹腔鏡下胆道閉鎖症根治術を導入後も、ある一定の条件を満たす患者さんに対しては腹腔鏡下で再手術を行っています。
2016年までに胆道閉鎖症に対する腹腔鏡下での再手術を7例行ってきましたが、全例で術後いったんは完全減黄(完全に黄疸がなくなること)という結果が得られました。
その後、やはり肝移植が必要となった患者さんが4例いらっしゃったため、再手術自体はまだ完璧な根治療法とはいえません。ただし、裏を返せば自己肝で生存されている症例もあるということができます。このことから、腹腔鏡下での再手術も一定の意義があると考えます。
自己肝での長期生存率はまだ高くはないものの、再手術しなければ患者さん全員が移植を受けなければなりません。できる限りご自身の肝臓を守るためにも、ある程度は再手術を行い、自分自身の肝臓で生活できる方法を考える必要があると考えます。
腹腔鏡下での手術により肝移植がスムーズになる?
腹腔鏡下での手術には、移植手術をサポートする面があることも判明しつつあります。
腹腔鏡下での手術後・再手術後に肝移植が必要となった場合はもちろん肝移植を行いますが、開腹手術で再手術をする場合、癒着(炎症などが原因で、分離しているはずの組織同士がくっつくこと)によってどうしても次のステップである移植が難しくなることが知られています。ところが、腹腔鏡下手術後の場合は開腹手術後とは異なり、肝臓の癒着が非常に少ないことが分かってきました。つまり、腹腔鏡下での再手術後に移植を行う場合は、従来の肝移植に比べて肝臓を摘出するまでの時間が非常に短くなっているのです。私は、この事実が腹腔鏡下手術の新たな利点となるかについて検討しています。
当院で腹腔鏡下での手術後・再手術後移植が必要になった方はまだ少なく、統計が取れていないものの、今後は腹腔鏡下手術の治療成績が開腹手術と遜色がないこと、また移植が必要な際でもスムーズに対応できることを示していきたいと考えています。
胆道閉鎖症の治療にはどのような方法が理想的か?
名古屋大学小児外科教授・内田広夫先生からのメッセージ
子どもの将来を考えたとき、子どもに精神的・肉体的な負担がかからない方法を選択することは非常に重要といえます。子どもの病気の治療で病院を訪れる際は、このことを意識していただきたいと考えます。